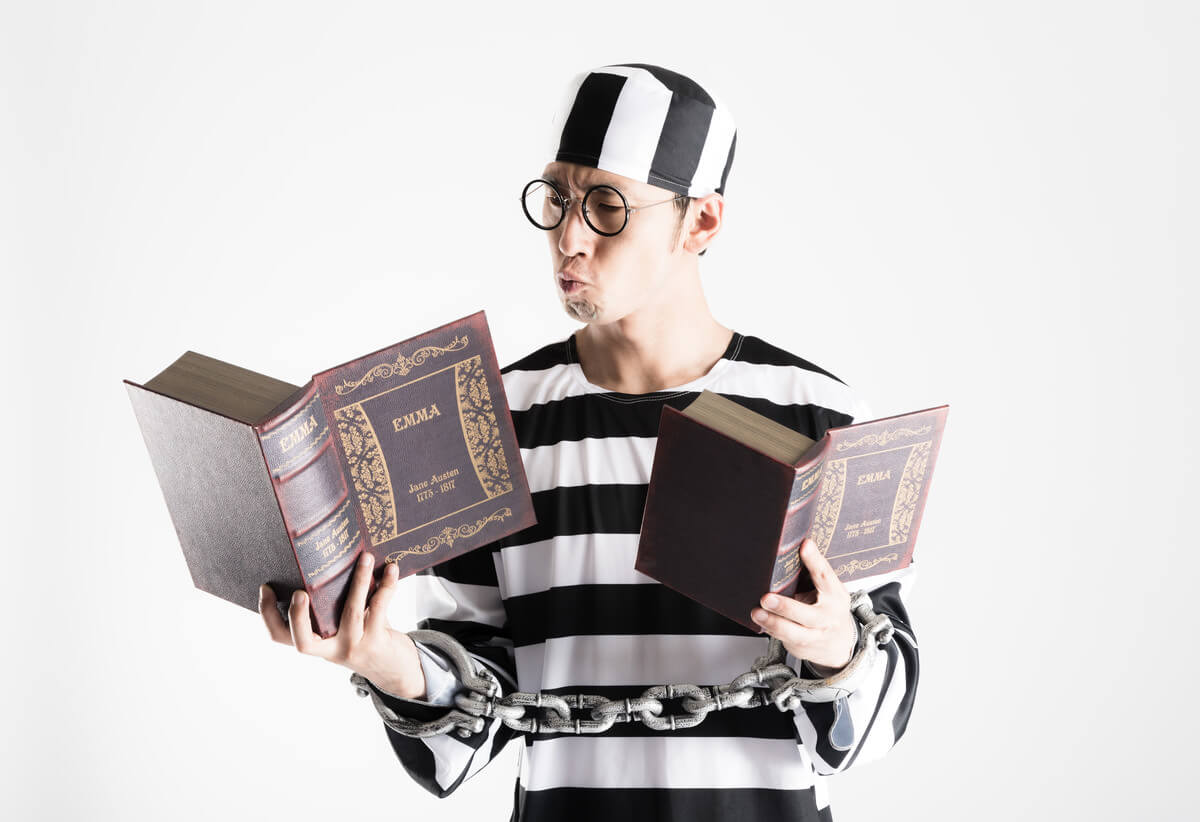

中小企業診断士試験合格のために過去問をやるべきと言われました。
果たして本当に過去問は効果的なんでしょうか?学習法に悩んでいるので教えてください。
こんにちは、あきっとです。今回は、このような疑問にお答えしていきます。
この記事で学べること
- 過去問の重要性がわかる
- 過去問をどの程度勉強すればよいかがわかる
記事の信頼性
働きながら、3年かけて中小企業診断士資格、2年かけて社会保険労務士資格を取得。
現在は企業に勤めながら、「副業中小企業診断士 兼 副業社労士」の個人事業主として活動中。
資格取得に苦労した立場から効率的な取得方法・活用方法などをお伝えして参ります。
≫プロフィールはこちら
結論:過去問は一次試験合格への第一歩
まず結論ですが、中小企業診断士試験に合格したいなら過去問をやりこみましょう。
過去問をやりこむことこそが合格の第一歩です。
ちなみにこの「過去問が合格への第一歩」という考え方、これは他のほぼすべての試験に当てはまると言っても過言ではありません。
この記事では、特に一次試験(択一)を中心にその理由を述べていきます。
なぜ過去問が重要なのか
あらためて、過去問がなぜ重要なのでしょうか?理由を3つあげます。
理由1:過去問こそ唯一の本試験問題である
あたり前ですが、過去に本試験で出題されたものが「過去問」です。
過去問以外に問題を解く材料として、各教育機関が出版しているオリジナル問題集などの試験対策本もあります。
しかし、オリジナル問題集の作問者と、本試験の作問者は異なります。
「過去に本試験でどのような問題が出題されているか?」そして、「過去問から何か出題傾向や意図を感じ取ることはできないか?」といったことを意識していきましょう。
まず本試験作成者がつくった問題をやりこむことで、その試験の傾向と対策を掴んでいくことが大切です。
理由2:本試験では類似の問題が出される可能性が高い
過去問をくり返し解くと、気づくことがあります。
それは、「過去に出題された問題が、くり返し出題されている」点です。
実はこれ、様々な試験でも見られますが、診断士の場合は次のような理由からと考えています。
類似問題が出題される理由(推察)
- 単純に、作問者が新たに問題を作成する作業が大変だから。
- 作問者は、過去に出題実績のある問題を出せば、国家試験として間違いはないと考えているから。
なお、中小企業診断士の作問者(試験委員)は、複数年に一度、交代されます。
新任者の場合、過去問と異なる論点を出題することに抵抗を感じる方もいるかもしれません。
以上から、本試験においても、過去問と類似の問題が出題される可能性は大いにあります。(まったく同じ問題も出ることも実際にあります)
類似問題が出てきたときは、絶好の得点チャンス。必ず正解できるようにしましょう。
理由3:本試験の「勘」が磨かれる
過去問に十分慣れていると、本試験でわからない設問に遭遇しても、正解の選択肢を選べる可能性が高まります。
一次試験は択一です。正解は選択肢の中に必ずあります。
理屈ではうまく説明できないのですが、過去問を体に染みつかせることで「出題者とシンクロする」とでも言うのでしょうか。
私は過去2回、一次試験を受けています。
本試験でまったく自信がない回答をしても、試験終了後に正解を数えていくと、不思議とわからない問題のほとんどが正解をしていました。
これは単なるヤマカンで片付ける話ではなく、過去問を体にしみこませた結果だと信じています。
体感して頂くことが手っ取り早いのですが、過去問をくり返すとこのような効果もあります。
過去問を何回やるべきか
結論としては、過去問は5回転させることをお勧めします。
時間がない場合であっても最低3回は回して、本試験に臨みましょう。
3回では、体に十分染み込ませるにはやや足りませんが、
それでも本試験で合格へ食らいつくギリギリのレベルまでは持っていくことは可能です。
なお、過去問の具体的活用法は別記事であげていますので、よろしければご覧ください。
まとめ
ここまで、過去問の重要性を述べてきました。参考にしつつ合格を目指ししてがんばってください。
ポイント
- 過去問は診断士試験合格への第一歩。
- 過去問を体にしみこませることで試験対応力向上が見込まれる。
- 5回は過去問を回すべし。難しくても最低3回は回そう。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
